年次有給休暇を取りやすい会社にするには、「制度面」「運用面」「職場風土」の3つに分けて施策を検討し、進めていくことをおすすめします。
年次有給休暇は年5日取得させる義務がある

2019年4月から、労働基準法第39条で、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して年次有給休暇の日数のうち年5日について、会社は取得させることが義務付されました。
しかしそれだけでは、社員が自発的に年次有給休暇を取得する環境にはなるとはいえないかもしれません。
厚生労働省も「働き方改革」の一環として、有休取得率向上を推進しています。
つまり、法令遵守することと、さらに社員が安心して休める環境づくりが企業の課題といえます。
有給休暇を「取りやすくする」ための施策の分類
施策は大きく以下の3つに分けて検討するのが効果的と考えられます。
- 制度面:仕組みとして取得しやすくする
- 運用面:日常業務で取得しやすくする工夫
- 職場風土:心理的に「取りやすい」文化をつくる
制度面:仕組みで「休みやすさ」を作る
※制度の導入については就業規則や労使協定の準備、その他に注意点等もありますのでご相談ください。
計画年休制度の導入
会社と労使協定を結び、年5日を超える部分について計画的に休ませる。(例:一斉、交代制、個人別付与など)
時間単位年休の導入
子の送迎・通院・家庭都合などに柔軟に対応可能(労使協定が必要)
(※時間単位年休は、年5日の取得義務付けの対象外)
半日単位の年休制度
1日の前半・後半で分割して取得できる(法令における制度ではないが推奨)
有休管理システムの導入
取得状況・残日数を「見える化」することで取得促進
運用面:日常業務で「休みやすさ」を後押し
管理職への研修
業務を回しながら、部下に有給を取得させるマネジメント研修を実施
有給取得状況の定期チェック
部署ごとの取得率を人事部がモニタリングし、偏りを是正
取得推奨日を設定
「有休推奨日」や「リフレッシュ休暇」を業務閑散期に設定。
上司による声掛け
「今月まだ有休取ってないよ」などの定期的なフォローをする
職場風土:心理的ハードルを下げて「休みやすい文化」をつくる
取得率を見える化
社内ポータルで会社全体の取得率を共有し、「有休は当たり前」の文化を作る
ロールモデルの発信
管理職が率先して有休を取得し、ポジティブに社内共有
有休取得理由をうっかり聞かない運用
年次有給休暇の取得に理由は問われませんが、ついうっかり理由を聞いてしまわないように徹底することで心理的な障壁を減らす
サンクスカード・表彰
休みを取りやすい職場づくりに貢献した社員・チームを評価
導入後の検証方法
施策の効果を確認するためには、KPI(重要業績評価指標)を設定することが望ましいと言えます。
※KPIとは、目標達成に向けたプロセスの進捗状況を数値で評価する指標のこと。
具体的には、以下のような指標が考えられます。
- 年間の有休取得率(政府目標:2028年までに70%以上)
- 部署別・課別・グループ別・チーム別などの有休取得日数の平均
- 取得者・未取得者のヒアリングによる心理的ハードルの分析
- 管理職ごとの部下の有休取得率
これらの指標を定期的に確認することで、施策が効果的に働いているかどうかを評価し、必要に応じて改善を行うことができるでしょう。
有給を取りやすい会社にするには現場への浸透が必要不可欠

有給休暇を「取りやすい環境」にするには、制度・運用・職場風土の三位一体の施策が不可欠といえます。
制度を整えるだけでは効果は不十分ともいえ、現場への浸透や管理職のサポートがあって初めて、社員が安心して休める職場になると考えられます。
有給休暇取得制度で悩まれている会社は、お気軽に魁マネジメントパートナー社労士事務所へご相談ください。
著者プロフィール
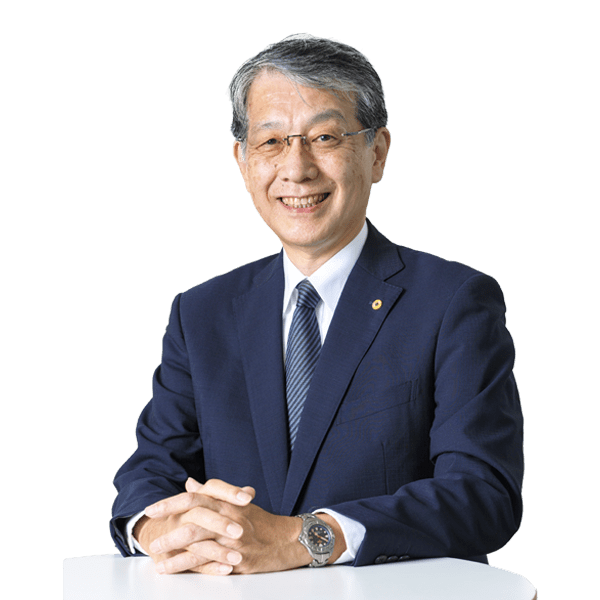
代表/特定社会保険労務士
岡村 俊彦
大手メーカーでのマネジメント経験後、社会保険労務士として独立。特定社会保険労務士・CFPとしての専門性を活かし、中小企業の労務トラブル解決や人材活性化を支援。ISO審査員補やYouTube出演の実績を持ち、年金・労務手続きから就業規則の策定、組織づくりまで幅広くサポート。
【保有資格】
・特定社会保険労務士
・ファイナンシャルプランナー CFP(R)
・プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー(R)
・医療労務コンサルタント(R)
・ISMS(ISO/IEC 27001) 審査員補
・OHSMS(ISO 45001:2018) 審査員補
